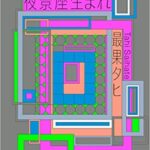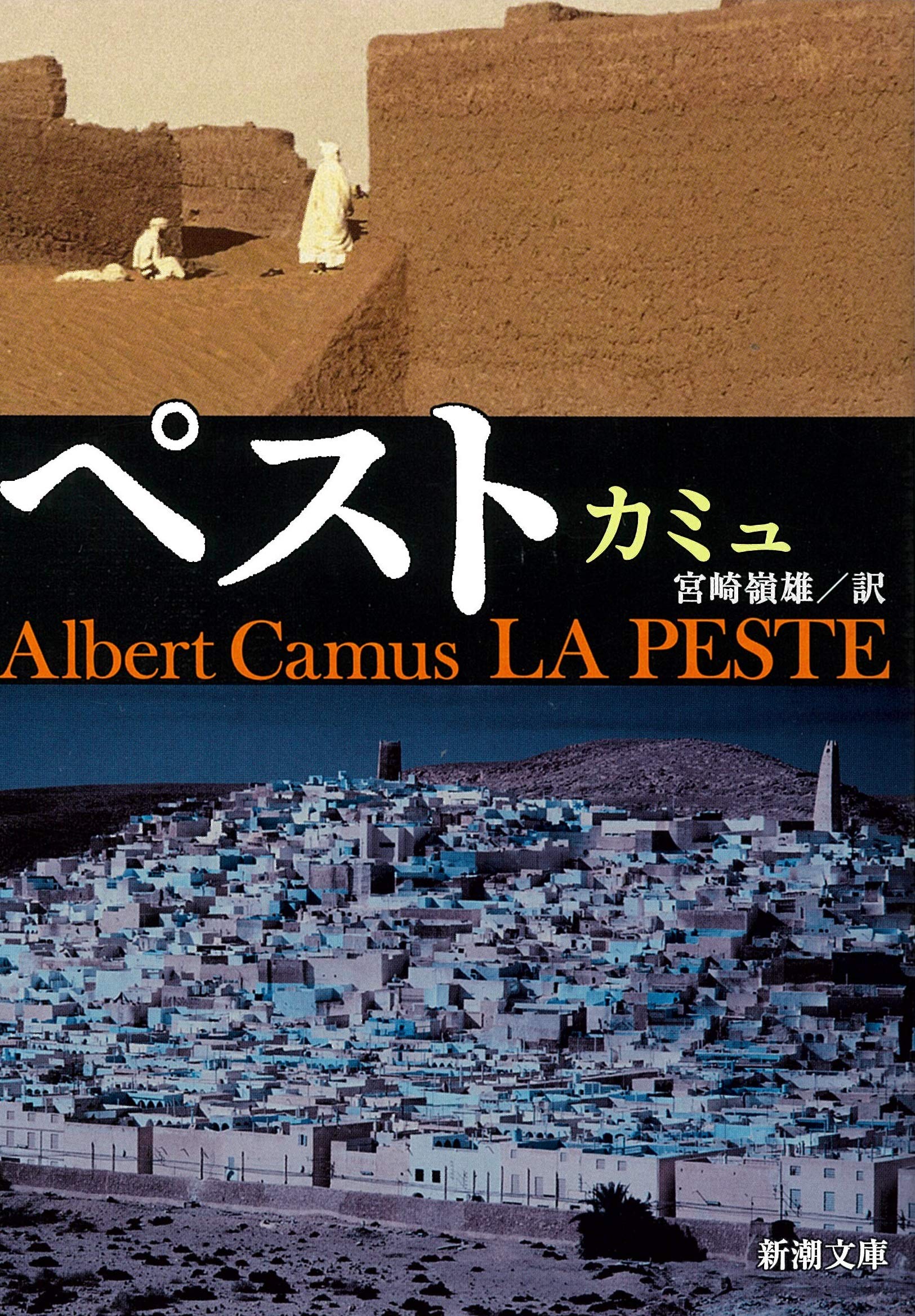
今、フランスのノーベル賞作家アルベール・カミュの『ペスト』が
飛ぶように売れているそうです。
この作品、出版されたのは1947年6月。
そう、今から約73年も前なんですね。
売れている理由はもちろん、「人間と疫病の戦い」を描いているので
コロナ禍を今まさに生きている私たちの生活と重なり合う作品だからです。
そんなに前に書かれた作品が、現在の私たちに響いているのが不思議な感覚ですが、
人間の恐怖の本質というのは、時代が経っても変化しないものなのだと心から思いました。
今回は、アルベール・カミュの『ペスト』をご紹介します。
目次
「ペスト」あらすじ
アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。
本文冒頭より
この記録の主題をなす奇異な事件は、一九四*年、オラン(訳注 アルジェリアの要港)に起った。通常というには少々けたはずれの事件なのに、起った場所がそれにふさわしくないというのが一般の意見である。最初見た眼には、オランはなるほど通常の町であり、アルジェリア海岸におけるフランスの一県庁所在地以上の何ものでもない。
町それ自身、なんとしても、みすぼらしい町といわねばならぬ。見たところただ平穏な町であり、地球上どこにでもある他の多くの商業都市と違っている点に気づくためには、多少の時日を要する。本書「解説」より
ペストに襲われ、外部とまったく遮断された一都市のなかで悪疫と戦う市民たちの記録という体裁をとったこの物語において、ペストの害毒はあらゆる種類の人生の悪の象徴として感じとられることができる。死や病や苦痛など、人生の根源的な不条理をそれに置きかえてみることもできれば、人間内部の悪徳や弱さや、あるいは貧苦、戦争、全体主義などの政治悪の象徴をそこに見いだすこともできよう。たしかにこの作品はそういうふうに書かれており、そしてなによりも、終ったばかりの戦争のなまなましい体験が、読者にとってこの象徴をほとんど象徴に感じさせないほどの迫力あるものにし、それがこの作品の大きな成功の理由となったことは疑いがない。
――宮崎嶺雄(訳者)
物語は一匹のネズミから始まります。
登場人物とそれぞれの苦悩が描かれた作品です。
ベルナール・リウー:医者
ジャン・タルー:よそ者
ジョセフ・グラン:作家
コタール:犯罪者
カステル:医者
リシャール:優秀医者
パヌルー:博士
オトン氏:判事
レイモン・ランベール:記者
喘息病みの爺さん:患者
それぞれの個性が描かれています。
カミュの『ペスト』は独特な世界感があります。
まさに希望がない絶望感だけで、物語りが進み、最後まで暗い話です。
そして不思議とその世界感が美しく見えてくるのです。
カフカの作品とも似ているところがあるのですが、
カフカは異色の世界感がある作品が多く、
特に『変身』に見られるように、終わらない日常をユーモア交えて表現している作品が多いのですが、
カミュにはユーモアがなく、
時代の空気感や生活感漂う文章で表現されています。
そういう意味でもこの時代に流行ったペストは
まさに悪夢で、絶望しかなく、人々の暮らしまでも変えてしまうほど恐ろしい病だったと思います。
登場人物も含め、それぞれの人生が狂ってしまう。
その中で希望を持って希望を望んでも希望が見えずに時代が終わる。
まさに絶望の中の絶望である作品だと思います。
そういう意味でも、コロナに類似点があるように思える一方で、
コロナよりも絶望感が強く、人々を不安させたペストの方がよほど怖い気がしました。
一匹のネズミの死体
全てここから始まります。
一匹のネズミの死体からやがて人間にも死者が出るようになり、
リウーがペストに気づきますが、当時は治療方法がなく医者たちは模索する日々を過ごしていました。
階段の下で死んだネズミ。
いつどのように死んだしまったのかわからないが、いつの日か人間にも移ってしまう。
それが最初の患者の喘息病みの爺さんだったのです。
そしてリウーの最初の患者となったのです。
そこからみるみる患者が増えていき、手に負えなくなってしまう事態に発展するとは
誰が想像できたでしょうか。
私はこの話しに出てくるネズミの場面が一番好きです。
なぜなら、たった一匹のネズミの存在がなければこの物語が始まらず、
何度もこのネズミが憎いと思ってしまうほど、ネズミのシーンが描かれています。
ある意味で主役の存在を発揮してくれるのがネズミの存在です。
日常的にネズミの死体がある街。
これを不思議と思う人はいない。
しかし悲劇はそんな日常からはじまるのです。
都市封鎖
新聞やラジオで情報を得る人々にやがて混乱が起きます。
人々はペストにかかったと言う患者を軽蔑し、
なんとかして街から離れようとして犯罪に手を伸ばす人。
自分の命と引き換えに家族と離れ離れになる人。
それぞれが意識を伝えようにも外出できない。
食料を手に入れるのにも一苦労する日々を過ごしていました。
通行証がないと出入りができなくなり、街から人が消えて、閑散とした中で、
生き続ける難しさと、愛が恋しく、寂しい気持ちを癒すものがなくなり、暗い日常となってしまった街。
噂はいつも誰が感染したか、誰が死んだかの話題で持ちきり。
新聞もラジオもその情報以外流れてこなくなり、
仕事も失い、お金はそこをつき
苦しい生活の中で食べ物を奪い合い、必死に生き抜こうとする人々。
そんな争いが尽きない生活の中で、希望を待ち望んでいる。
そんな場面が描かれている部分が一番読むのが辛かったです。
医者たちの苦悩
リウーをはじめとする医者たちは、患者を救うのか患者を見捨てて自分だけ生き残るのか、
そして自分の家族も見捨てるのか、様々な苦悩が細く描かれています。
そして患者が増えるごとに絶望し、死者との向き合い方にも変化が訪れます。
手厚い医療も患者が増えるごとに、命の選別をしながら治療していく。
生き残れる患者がいない現実に懸命に新薬の実験をするリシャールとリウー。
いつの日か2人の間に希望が見えてくるのです。
そしてこの戦いにも終わりが見えてくる。
それは絶望から希望のはずだったが、終わっても、まだ終わってない。
なんとも切ない戦いの終わりでした。
いかがでしょうか?
『ペスト』のあらすじだけでも、今まさにコロナと私たちが戦っているのと
同じ状態が繰り広げられていますよね。
出口がいまだ見えないコロナ危機において、『ペスト』というフィクションの中に
コロナという疫病における恐怖、大幅に行動が制限されている心理状態、
これまでに経験したことのない戸惑いなど私たちのノンフィクションの日常を投影しているのです。