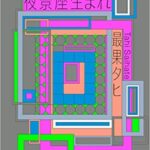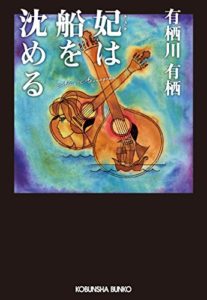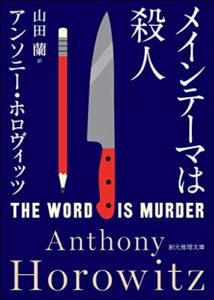小川糸さんの作品には
独特の世界観があります。
それは、「暮らし」が細部に渡るまで
とても丁寧に描かれているところ、
そして、「食」が大変愛おしく
捉えられているところです。
それらを通して、
どの作品からも伝わってくるのが、
ひだまりのような温もりや木漏れ日のような優しさ。
こんなふうに穏やかに丁寧に毎日が送れたらいいな、
こんな洗いざらしのシーツのような
素直な気持ちで日々生きられたらいいな、
とつい思わせられてしまう、
そこが糸さんの魅力ではないでしょうか。
そんな糸さんが「死」をテーマに書かれた小説があります。
その作品が、この「ライオンのおやつ」です。
糸さんらしく、
やはり「おやつ」という「食」に
スポットを当てた物語で、
ホスピスでの日常の描写をこのようには、
糸さんでなければ書けなかった物語だと思います。
目次
「ライオンのおやつ」あらすじ
人生の最後に食べたいおやつは何ですか――
若くして余命を告げられた主人公の雫は、瀬戸内の島のホスピスで残りの日々を過ごすことを決め、穏やかな景色のなか、本当にしたかったことを考える。
ホスピスでは、毎週日曜日、入居者がリクエストできる「おやつの時間」があるのだが、雫はなかなか選べずにいた。
――食べて、生きて、この世から旅立つ。
すべての人にいつか訪れることをあたたかく描き出す、今が愛おしくなる物語。
穏やかな海とそこに映る太陽の光、
遠くに見える丸い島と青い空に
ぽっかり浮かんだ雲。
手前の緑はレモン畑でしょうか、
黄色い実が灯りのように点々と、
そしてその岸から一艘の舟が
沖に向かってすすんでいます。
水彩画のようなふんわりと描かれた
そんな表紙と「ライオンのおやつ」という
絵本のようなタイトルから、
誰がホスピスでの物語だと想像できましょう。
ここは瀬戸内にある一つの島。
主人公の雫はまだ30代前半という若さで
余命を告げられ、
この島にあるホスピス「ライオンの家」
にやってきます。
ここには何も規則はなく、
自由に時間を過ごす、
というそれだけが唯一のルール。
そしてこの「ライオンの家」には、
毎週日曜日におやつの時間が設けられていました。
入居者がリクエストするおやつです。
しかしそれはただのおやつではなく、
希望する人ができるだけ詳細にそのおやつに
ついて紙に書き、
リクエストをするというやり方。
そのおやつをここで再現という形で
手作りされるのです。
どのおやつにもそれをリクエストした人の思いと
エピソードがぎゅっと詰まっていて、
おやつの時間に粛々とそのおやつを共に食することで、
その人の生きてきた時間を尊びます。
人生の最後に、自分が希望して食するおやつと
いうものに焦点を当てながら、
死へ向かうこと、生きること、
が雫の目線や心の動きから
たおやかに描かれています。
ライオンの家に思うこと
瀬戸内はもともと温暖な気候で、
海も波がほとんどなく穏やかで美しいところ
だと聞いてはいましたが、
なにしろ訪れたことがないので、
この本を読んでまず瀬戸内の島に
行ってみたくなりました。
実は読み終えてすぐに、
この島はどこなのか、
このホスピスは実在するのかと
調べてしまったぐらいです。
そして島の美しさに負けず劣らず、
このライオンの家のオーナーである
マドンナという女性が素晴らしい。
喜怒哀楽は表に出すことなく
常に淡々と仕事をしているのに、
非常に温かく感じられる人間像からは
本当の意味でのやさしさが垣間見られ、
心から信頼したくなる人だと思いました。
入居者たちはもちろんそれぞれの
これまでの人生があり、
その人生の物語にいよいよ幕を
下ろそうとしている人たちで、
ここにいるそんな人たちからのリクエストに応え、
忠実に再現すべく心を込めて作られるおやつには、
おやつと簡単に言うけれど、その一つ一つに、
このホスピスで最期を迎える人一人ひとりが
生きてきたエピソードがしっかりと
包み込まれたものばかり。
こんなに感慨深いおやつとは、
これまでのおやつの概念をすっかり変えて
しまうほどのものでもあり、
死とおやつという、
一歩間違えば少し違和感を覚えるかもしれないところを、
死を迎えるという背景の中で
それを食すという行為がとても丁寧に
描かれていることで、
逆に食に対しても生に対しても死に対しても
敬意を払っているように感じられました。
「どっち側からドアを開けるかの違いだけ」
雫がライオンの家に到着するまでの間に、
道中、マドンナから言われた
「生と死は背中合わせ」
わかりやすく言うと
「どっち側からドアを開けるかの違いだけ」
という言葉にまず序盤から
胸を撃ち抜かれました。
そして一貫して死を恐れるものとしてでなく、
生と死を繰り返してぐるぐる回っている生きもの
として私たちを捉えているマドンナの態度や姿勢に、
私自身、大変救われるような気持ちになりました。
雫が余命を宣告され、
それを受け入れるまでの葛藤は計り知れません。
想像するだけでも涙が溢れて止まりません。
ですが最後、
このような場所でこのような人々に出会い、
生とは反対側のドアを開けに行く日まで、
こんなに美しく落ち着いた気持ちで
過ごしていけるということは、
人生の長さとは別に、
なんて幸せなことだろうと思いますし、
憧憬さえ抱いてしまいます。
読み進むにつれ、ここがホスピスである限り、
日々弱っていく雫にも、
他の入居者の方の変化にも、
どうしても涙はぬぐえませんが、
誰にでもやってくるその時に向けて、
この小説は私のバイブルのような一冊
になりました。
この記事を読んだ方はこちらもオススメです↓