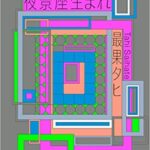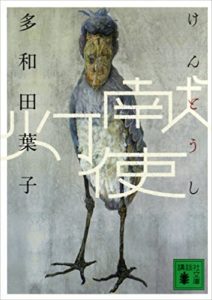今回ご紹介する一冊は、
原田マハ 著
『ジヴェルニーの食卓』です。
作者の原田マハさんが
「史実をベースにしたフィクション」
と呼ぶ作品群に属し、
主に印象派と見なされる有名画家たちの、
生涯のエピソードに基づく短編集です。
取り上げられる画家たちは
マティスにピカソ、
エドガー・ドガとメアリー・カサット、
セザンヌにヴァン・ゴッホ、
そしてクロード・モネです。
誰もが聞いたことのある名前
ばかりではないでしょうか。では。
目次
原田マハ『ジヴェルニーの食卓』「美しい墓」
ジヴェルニーに移り住み、青空の下で庭の風景を描き続けたクロード・モネ。その傍には義理の娘、ブランシュがいた。身を持ち崩したパトロン一家を引き取り、制作を続けた彼の目には何が映っていたのか。(「ジヴェルニーの食卓」)新しい美を求め、時代を切り拓いた芸術家の人生が色鮮やかに蘇る。マティス、ピカソ、ドガ、セザンヌら印象派たちの、葛藤と作品への真摯な姿を描いた四つの物語。
若かりし頃、
晩年のマティスの元で
家政婦を務めた老女が語る、
マティスとピカソの最後の邂逅の物語。
画が好きだった戦災孤児の少女マリアは、
それもあってマティスのパトロンでもあり、
美術品コレクターでもあった、
裕福な寡婦の元で働き始める。
あるときマダムの命を受けた彼女は、
マティスの元へマグノリアの花束
を届けたのだが……。
始めに登場するのは
フォーヴィズムの創始者
アンリ・マティスです。
マティスと言えば野獣(フォーヴ)と
称された強烈な色彩を
思い浮かべる方が多い
のではないでしょうか。
お話のキーになるのは
マグノリアの白い花です。
使いに出されたマリアは、
画家に言われ、
思いつくままにこの花を活けたのですが、
それが偶然マティスの絵画
「マグノリアのある静物」
そっくりだったのです。
このことから画家に
気に入られたマリアは、
彼の元で働くことになります。
マリアは二度ピカソと出会うのですが、
そのたびにマグノリアの花が
印象的な使われ方をします。
どんな使われ方をするのかは、
どうぞ本作をお読みください。
老嬢の話し言葉をそのまま写した
という体を採る、
色彩感にあふれる文章が魅力的です。
原田マハ『ジヴェルニーの食卓』「エトワール」
エドガー・ドガが亡くなり、
彼の遺品を整理していた画商から
メアリー・カサットの元へ連絡が入る。
印象派のアメリカに於ける
受容に尽力した、
今は老いたこの女流画家にとって、
ドガは最も重要な導き手であり
ライバルだった。
画商が彼女に見せたかったのは
蝋で創られた、幼い踊り子の像。
それはかつて印象派展に出品され、
ごうごうたる非難を巻き起こした
「十四歳の小さな踊り子」だった。
ここではドガとメアリー・カサット
という二人の画家が登場します。
印象派の歴史の上で、
この二人の師弟関係は有名で、
作中にあるドガのパステル画を
「ショーウィンドウに鼻を
ぺちゃんこにくっつけて」見たという、
カサットの手紙は実在のものです。
けれど史実は、カサットがドガの
絵画制作のやり方をほんとうのところ、
どう思っていたのかを教えてはくれません。
ドガは本職のモデルでさえない、
貧しい踊り子を雇って
ヌードデッサンの対象にしていたのです。
「十四歳の小さな踊り子」のモデルだった
マリー・ヴァン・ゴーテムもそうでした。
〝女の画家〟と言うものに対する
世間の無理解と
闘わなければならなかったカサットは、
当然最初期のフェミニストです。
その彼女の目に、
ドガのデッサンは
どう映っていたのだろうか?
という簡単には答えの
出なさそうな思考実験が、
このお話の出発点のような気がします。
原田マハ『ジヴェルニーの食卓』「タンギー爺さん」
タンギー爺さんの娘から
セザンヌの元へ手紙が届く。
画材店の店主でありながら、
若い画家たちに肩入れし、
売れそうもない画を引き取っては
代わりに絵の具を渡してしまい、
店の赤字にはどこ吹く風の爺さん。
娘はセザンヌにとにかく溜った付けを
払ってくれと嘆願し、
更に新しく爺さんが肩入れしている、
ゴッホとかいう画家のことを――。
今度の主役は画家ではありません。
浮世絵を背景にしたゴッホの肖像画で
知られるタンギー爺さんは、
パリの画材店の店主です。
お話は彼の娘がセザンヌに送った
借金の督促状の体を採ります。
そうして爺さんの店で起きる様々な
事件のスケッチ、
ゴッホによる肖像画制作や、
彼らの絵画談義、
更にはエーミール・ゾラの
「制作」事件……。
ラストに漂う祭りの後のような寂寞感
には胸が締め付けられます。
原田マハ『ジヴェルニーの食卓』「ジヴェルニーの食卓」
富と名声を得、
南仏の広大な自宅に籠もって、
悠々自適で過ごすかに見える、
晩年のモネ。
けれど視力に問題を
抱えていることもあって、
芸術家としての彼の苦悩は
過去のものではなかった。
亡くなった母に代わり、
そんな彼に寄り添い支えるのは
娘のブランシュ。
けれど彼女がモネの娘になるまでには、
簡単には語れない物語があった。
印象派と一括りにされていても、
実際にはそもそも
印象派でなかった画家
(たとえばドガ)や、
印象派から離れていった画家
(たとえばセザンヌ)
がいて、
徹頭徹尾印象派だった画家は
それほど多くありません。
その一人がクロード・モネです。
ここでテーマになるのは彼の生涯で
最も印象的な出来事、
それは友人のエルネスト・オシュデとの間
で起きました。
裕福だった頃はモネの
パトロンだった
この元百貨店主は、
破産をし、無一文になると、
モネの元に自分の妻子を置き去りにして、
自分はベルギーに去ってしまったのです。
残された妻のアリス・オシュデは
夫ではなくモネを選んで、
夫の死後、モネと再婚します。
書きようによっては幾らでも
ドロドロになるこのエピソードを、
作家は最初はブランシュ・オシュデという
少女だった女性の目を通して、
淡く書き上げています。
本作の中でモネが描いている
「睡蓮」の連作は二百点以上あるそうで、
日本の何点かが存在します。
わりと近くの美術館でも
公開されているんですが、
また見に行こうかな。
この記事を読んだ方はこちらもオススメです↓