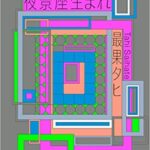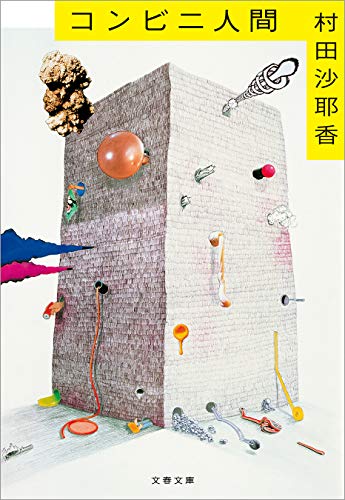
今回ご紹介する一冊は、
村田 沙耶香 著
『コンビニ人間』です。
去る7月15日、
第163回芥川賞と直木賞が
発表されましたが、
こちらの『コンビニ人間』は
第155回芥川賞を受賞した作品です。
2016年ですので、4年前。
世の中の移り変わりが速すぎて、
たった4年なのに当時のコンビニと
現在のコンビニはもう違うところ
もあったりします。
セルフレジの普及や夜間無人コンビニ、
新しいところではレジ袋の有料化。
通り一遍の無機質な存在のように見えて、
実は内容の代謝が非常に激しいコンビニ。
最も幅広い年齢層に最も愛され、
おそらく誰もが立ち寄ったことのある
コンビニというお店を舞台に、
コンビニ店員の主人公を通して、
人間らしさや社会で生きる意味
を問う本作品は、
世界的にも高い評価を得て、
なんと24か国語に翻訳されること
が決定しています。
目次
村田沙耶香『コンビニ人間』あらすじ
第155回芥川賞受賞作!
36歳未婚女性、古倉恵子。
大学卒業後も就職せず、コンビニのバイトは18年目。
これまで彼氏なし。
オープン当初からスマイルマート日色駅前店で働き続け、
変わりゆくメンバーを見送りながら、店長は8人目だ。
日々食べるのはコンビニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、
清潔なコンビニの風景と「いらっしゃいませ!」の掛け声が、
毎日の安らかな眠りをもたらしてくれる。
仕事も家庭もある同窓生たちからどんなに不思議がられても、
完璧なマニュアルの存在するコンビニこそが、
私を世界の正常な「部品」にしてくれる――。ある日、婚活目的の新入り男性、白羽がやってきて、
そんなコンビニ的生き方は
「恥ずかしくないのか」とつきつけられるが……。現代の実存を問い、
正常と異常の境目がゆらぐ衝撃のリアリズム小説
コンビニバイト歴18年の古倉恵子は、
37歳独身。
幼い頃から周囲に普通ではないと思われ、
家族からは治ってほしいと悩まれ、
「皆が不思議がる部分を自分の人生から消していくことが治るということなのかもしれない」
と感じながら、
それでも具体的には
どうすればいいのか
わからないまま生きてきた恵子は、
コンビニという「小さな光の箱」の中で
完璧なマニュアル通りに従って
働いてこそ生き生きと輝きます。
コンビニの奏でる音が大好きで、
キラキラしたコンビニの店内が大好きで、
勤務していない日や帰宅後でさえ、
コンビニで働く明日のために体調を整え、
栄養を摂取し、睡眠を取る・・・。
アルバイトという立場でありながら、
そんな、自分のすべてをコンビニに
捧げる日々を送っていたある日、
社会に対するただならぬ憤懣を
全身に湛えた白羽という男性
に出会います。
自分を異物だといい、
自分のような異物を認めようとしない
現代社会など、
縄文時代のムラ制度から何も変わってはいない
と怒り苦しみ、
それでも社会に受け入れられるための
無茶苦茶な人生設計を立てる白羽に、
半ば共感し半ば反発し、
影響されながら恵子には
新たな日常が始まるのですが・・・。
村田沙耶香『コンビニ人間』果てしないコンビニ愛を疑似体験する
主人公、恵子の生き方を理解できるか否か、
あるいは肯定できるか否かは別として、
まずは大変身近なコンビニという場所が、
素晴らしく愛に満ちた描かれ方を
していて感動しました。
この「透き通ったガラスの箱」
のオープン当初は
「まるで作り物ではないかと思うほど綺麗に並んでいた食べ物やお菓子の山が、『お客様』の手であっという間に崩されていく。どこか偽物じみていた店が、その手でどんどん生々しく姿を変えていき、」
恵子は自分を含めたコンビニ店員のことを
「同じ制服を着て、均一な『店員』という生き物に作り直され」
制服を脱いで元の状態に戻ると
「他の生き物に着替えているように感じられた」
と面白がり、
コンビニが作動しているときの音、
例えばドアのチャイムや店員のあいさつ、
パンの袋を握られる音やペットボトルが
カラララとローラーで流れてくる音、
レジでの小銭の音や客の靴音などを
全身で感じ取っています。
そしてアルバイトであっても
18年間も勤務していると、
コンビニが何を求めているのか、
コンビニの声までもが聞こえて
止まらなくなるというのです。
完璧なマニュアルのもとに
初めて機能する無機質な店、
まるで「宗教のような」
コンビニという場所を、
そしてそこで働くことを
恵子がこよなく愛している、
という事実が、
一つひとつの表現から
ひしひしと感じられ、
まるで読みながら
疑似体験をさせてもらっているようで
とても興味深かったです。
村田沙耶香『コンビニ人間』まともって何?まともじゃないとどうなのか
なぜ恵子はこんなにもコンビニを愛し、
そこでしか働くことができなかったのか・・・
それは、コンビニとは
完璧なマニュアルがあり、
それに従うことで個性が画一化される
場所だからです。
そういう職場だからこそ、
安心して身をおくことができたのです。
なぜなら恵子は、
公園で死んでいた小鳥を
埋めようという友達に対して、
食べようという子どもでした。
家族が焼き鳥が大好きだから、
わざわざ買いに行かなくても
せっかく死んでいる小鳥を
食べればいいのに、と。
そして可哀そうだからと死んだ小鳥
にお墓を作って、
そこらの花を引きちぎって殺して
お墓に供える友達の行動を
理解できずにいました。
そんな、子ども時代から
「普通」じゃない
と言われ続けた恵子は、
そう言われ続けるがゆえに
「自分はまともではない」
「社会不適合者なのだ」
と自覚もしていました。
一般的に社会では
どう振る舞えばいいのかは、
妹が指示を出してくれていました。
しかしそれを深刻に悩むわけでも
苦しむわけでもない恵子の感情には、
非常に興味をそそられるものがあります。
途中から関わりを持つことになる
白羽の義妹が、
結婚も就職もせずに
36年間生きてきた恵子に向けて
「その腐った遺伝子、寿命まで一人で抱えて、死ぬとき天国に持って行って、この世界には一欠けらも残さないでください」
と罵声を浴びてきても、
そうかと納得し
「私の遺伝子は、うっかりどこかに残さないように気を付けて寿命まで運んで、ちゃんと死ぬときに処分しよう」
と、淡々と決意するのです。
作中に繰り返し出てくる
「結婚」と「就職」こそが
社会と正しく繋がることであり
社会の為である、というくだりに、
私は常識とか非常識とか、
正常とか異常とか、
社会的にまともかそうじゃないかは、
ただのマジョリティか
マイノリティかの違い
ではないかと言いたくもなりますが、
自己のマイノリティ性を
必死に正当化
しようとする白羽に対して、
同じマイノリティでもそれを
苦にすることなく、
ただ外野の声に、
それに従った方が皆安心するのだろう、
それにはどうしたらいいのだろう?
と思いつつも、
特に積極的に悩むわけでもなく、
コンビニという最も居心地の良い場所で
社会の部品となって生き続ける恵子、
この二人の対比には
考えさせられるものがあります。
この記事を読んだ方はこちらもオススメです↓